|
寺山は俳優と作家の役割を転倒させることで、「壁の隙間」を極限まで押し拡げてきた。そのためには、稽古場で俳優とともに戯曲を練り上げる、長期の演出に関わる必要があったと言える。だが、この演出の作業が困難になるときがやってくる。持病の肝硬変の悪化である。
――言葉といえば、このお芝居には非常に言葉、台詞が多いですね。
寺山さんが演出活動を休んで、後の演出はシーザーに任せる、自分は戯曲に専念するんだという休養宣言をする。この『レミング』という作品は、その休養宣言の、ちょっと前の作品なんですよ。病気で体力が衰えて、「俳優の演技を総合して脚本化する」という手法が採れなくなったとき、おそらく彼は、戯曲に対して従来とは違った手法を取り入れようと考えた。そのきっかけになった作品が『レミング』なんです。だからこの作品には台詞が非常に多いんですよね。
――ものすごく饒舌なんだけれども、合間合間にふっと言葉が聞こえてきて、それがイメージに結びついていくような感じですね。
そこにあるのは、「言葉はいくらあっても構わない。ただ、台詞の隙間からふっと聞こえてくる大事なものさえ聴き取れればいいだろう」、という考え方です。だからほとんどビジュアル系の言葉というか、全体の構図を思考させる言葉、絵のためのエネルギーになる言葉が中心で、大事な部分だけ聞こえるようにしてある。
――寺山さんがこれを制作されてる時点で、おそらくもうご自身の究極の壁、つまり「死」っていうのを意識されてたと思うんですが……。
だから遺言じゃないけど、演劇界に対する一つの遺しもの、という気はします。『奴卑訓』から『邪宗門』、さらには『百年の孤独』に至るまでの総集編のような気はしますね、この作品は。
――実は僕、このお芝居をはじめて拝見したのは、高田さんの演出された、名古屋の七ツ寺共同スタジオ版だったんです。あの『レミング』と今回とではすいぶん印象が違って、大変もの悲しい、メランコリックな印象を受けたのですが……。やはりそこには、寺山さんに対する思いの違いといったものがあるんでしょうか。
僕の場合、寺山修司をレンズとして世界を見てきたと思うんですよ。単に寺山さんの思考とか思想をレンズとするんではなくて、寺山修司そのものというかな、彼の日常そのものをレンズ化してきたと思うんです。よく「寺山さんてどんな人ですか」って聞かれるけど、僕はもう寺山さんと一緒の人なんで、だからどんな人って言われても答えようがないですよね。自分に重なってきた人というか、僕が重なり合っていったというか……。寺山さんの中に縦にどんどん自分が入り込んでいくと、その中に僕がいて、さらにその中に寺山さんがいてしまうという、そういう構造だったような気がするな。
――寺山さんって一種魔術的というか、関わった人がみんな、ある種人生が狂っていくというか(笑)、そういう魔力がある方だとと思うんですけれども、今でも無条件に寺山さんを信頼されてらっしゃいますか。
してますね。例えば彼は、同じ作品をどんどん構造を変えていくんです。パリに行ったときも、オランダやポーランドに行ったときも、劇場に、それからその街の雰囲気に合わせよう、東京で作ったものを東京というサイドから提示するのは演劇ではない、という考え方でした。だからこのお芝居にしても、初日とはずいぶん変わってるんですよ。舞台の下手に、高くなったところがあるでしょ? あれは本来、上下に二つあったんですよ。それを今回は上手の方は平らにしてある。それで、上手の舞台でやってた芝居を、花道の上でやってるんですよ。次のサンシャインではこれは全部なくなって、真っ平らになりますからね。牧野君は今度は平らなとこの下から顔を出すことになる。
いま何を信頼していいか判らないような時代だけど、「寺山修司がいまこれをこの劇場で作ったらこうしただろうな」ということは、知らず知らずのうちに染みついてますね。

|
リハーサル風景:中華鍋と高田惠篤氏
|
今回上演された『レミング』では、「出口なし」の絶望的な状況が繰り返し描かれる。そのエンディングの陰惨さは、既に「出口主義ふたたび」という文章で記しているので、ここでは繰り返さない。とはいえ、そんな陰鬱なフィナーレを迎える『レミング』においても、寺山は登場人物にこんな台詞を喋らせている。
「あたしは出口。あなたの出口。東京地図の尋ね人。鉄道郵便局の受取人不明の郵便物の中に隠れている」。
偶然にデッドストック空間に迷い込んだ、宛先不明の手紙(デッドレター)。確率論的な偶然による他者との出会い。そこに寺山は、壁からの出口、壁の隙間を見いだしていたのだ。振り返れば、寺山はその生涯にわたって、何度も何度も「郵便」というモチーフを取り上げている。「盲人書簡」、書簡演劇、あの世への郵便配達夫、ニセ絵葉書……。谷川俊太郎氏のもとには、寺山の死から数年後にも、寺山からの手紙が届いたという。おそらくこれほど「郵便的」な作家も珍しいだろう。寺山は徹底した「出口なし」の状況を描きながら、宛先不明の手紙という、奇妙な出口に取り憑かれた人間でもあったのである。また寺山は別のところで、こんなことも書いている。
「劇は『出会い』である。『出会い』を必然としてとらえようとするのが政治学であるとするならば、われわれはその対極において、『出会い』を偶然的なるものと認識する。(略)……かぎりなく交錯する出会いの偶然性を、想像力によって組織すべく、われわれは旅立つものだ」。
彼にとって演劇とは、確率論的な偶然の出会いを、組織化して行う行為に他ならなかったのである。そんな彼が、自らの「死」という最後の壁を目の前にしたとき、宛先不明の手紙を託した郵便配達夫。それがJ・A・シーザーだったのだと書けば、あまりにも感傷的なまとめ方だと笑われるだろうか。いずれにせよ、「壁」の存在も「郵便」という脱出口も、彼にとっては単に抽象的なテーマではなかった。自分自身の「死」という実存的なテーマと切り離せない、具体的な課題だったのである。>>次頁
page 4/5
|
『奴卑訓』
ついさっきまで主人だった人物が奴隷となり、奴隷だった人物が主人となる……。真の主人はとうの昔に殺害されており、「不在の主人」の座を奴隷が順番で演じるという奇妙な制度を描いた作品。「不在の主人」をめぐる不可解な制度は、三島の天皇論やバルトの「空虚な中心」論を連想させる。海外公演も含めて100回以上上演された。アップリンクにてビデオが販売中。本体価格¥5800円+税。

『邪宗門』
初期の土俗的作品の集大成。結末では俳優陣が劇を演じるのを止め、自分の言葉を喋り出す。「革命の演劇から演劇の革命へ」という名台詞で有名。サントラが書籍つきCDとして、ブルース・インターアクションズから再販。(ISBN4-938339-58-7 C0073 \3300E)
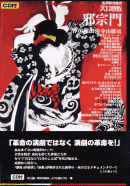
『百年の孤独』
G・マルケスの『百年の孤独』に想を得た書き下ろし作品。4つのステージで独立した劇がかわるがわる演じられる複雑な構成で、一見しただけではストーリーの把握がほとんどできない。このため、アップリンクにて販売されているビデオには、上演台本が付録として添付されている(税込み¥5800)。内容的には『奴卑訓』で明らかにされたのが寺山の空間論であったのに対し、寺山の時間論を語るものとなっている。なお、この作品の主要モチーフは、後に寺山の監督した映画『さらば箱船』に受け継がれている。

牧野君
牧野公昭氏のこと。1978年「天井桟敷」入団、寺山のさまざまな舞台作品・映画作品に出演。万有引力を経てフリーに、現在は実相寺昭雄監督の映画作品のほか、宮本亜門の舞台や一人芝居などを精力的にこなしている。この公演では地下に監禁されている主人公の母親役を演じた。
|