|
|
|
多重人格探偵サイコ オウム真理教的、宮崎的
■本物への戦慄、規格品への戦慄とはいえ、大塚英志はお気楽に反時代的であることを装ったり、「内面の復権」を叫んだりはしない。例えば『サイコ』の登場人物たちを、「過剰な内面の爆発」の典型である『あしたのジョー』の登場人物と比べてみればいい。力石徹は矢吹丈を見て「本物だった」と戦慄するが、『サイコ』の登場人物たちは全く逆に、「規格品だった」と戦慄する。彼らは矢吹丈や力石徹のように、一切の欲得抜きで「ひとりの男の持つ全て」をぶつけあったり、「もつれ合うように生き」たりはしない。規格品として大量生産された人間が、そんなことをできよう筈がないのである。 そもそも『サイコ』という作品自体、作者の体験の反映などではなく、TVドラマやハリウッド映画、せいぜいリアルなところで60年代以降のサブカルチャー、現実の殺人事件からの引用の集積でしかない。『サイコ』の登場人物に刻印されているのは「過剰な内面」などではない。むしろそこにあるのは救いがたいまでの平板さであり、「深みのなさ」なのである。そしてこの「深みのなさ」は、そのまま俺たち自身の抱える不毛にも直結している。俺たちは戦争を知らず、飢餓を知らず、貧困を知らない。ベトナム戦争もヒッピー・ムーブメントも、バブル経済すらロクに知らない。後ろを向いてもそこにあるのは模造品と規格品、乱反射するシミュラークルの戯ればかりなのである。 俺たちの生を構成する経験は規格品でしかなく、その順列組み合わせによってしか俺たちは自己を語れない。だが、仮に自分が全くの規格品から出来ていたとしても、それでも「自分」という存在、「自分とは何か」という問いは残る。この問いから逃げようとすれば、完全にデータベースの中に自己を溶解させる「宮崎的なるもの」の誘惑が待っている。 手許に残された大量のジャンクだけを頼りに、「宮崎的なるもの」の誘惑を振り切って、「自分とは何か」を語ることは可能か。大塚が『サイコ』を通して問いかけている問いは、まさにこの点にある。あくまで「深み」や「内面」を欠いたところから出発し、規格品の記憶だけを頼りに「自己」を語ること。この救いがたくチープかつ深遠な問いを巡って、『多重人格探偵サイコ』は綴られている。そしてその暴走は、一部の読者を置いてけぼりにするほどの速度にまで達しているのである。  【図5】 【図5】シトロエンにハコ乗りして爆走する西園信二。集中線をいっさい使わずにこのスピード感を表現する、田島昭宇の画力に注目。『サイコ』前編を貫く疾走感は、田島のこの卓越した画力に支えられるところが大きい。 『多重人格探偵サイコ』より (c) 田島昭宇/大塚英志 ■宮崎的なるもの、オウム的なるもの最後に、このジャンクな時代にあって、「宮崎的なるもの」と双璧をなすもう一つの誘惑、「オウム的なるもの」について、大塚がどのように考えているかを確認してこの稿を終えたい。大塚はその著書『彼女たちの連合赤軍』の中で、オウム真理教の女性信者たちの多くが編集者やライター、エステティシャンなどの「カタカナ職業」であったことに着目し、しかも彼女たちが「カタカナ職業」のなかでも最底辺に位置する「おちこぼれ」だったと指摘している。彼女たちはこうした職業に就けば「自己実現」ができると思いこんだのであり、そしてそれに挫折した人間たちだったのだ。彼女たちはまた、「カタカナ職業」に挫折すると同時に、カタログ雑誌の「消費による自己実現」にも疲れ果て、挫折した過去を持っていた。彼女たちは、「消費」と「労働」の双方から疎外された人間たちだったのだ。 こうした二重の疎外の底に呻いていた彼女たちは、オウム真理教に飛びつくことになる。「カタカナ職業」や「消費による自己実現」といった現世的なものの向こうに、神秘的な「深み」を湛えた何かがある、とオウムはささやいた。そしてそこにこそ本当の「自己」がある、とつぶやいてみせたのだ。彼らは宮崎とは全く正反対に、全く虚構のチープな「自己」像を仮構し、彼女たちに与えたのである。 言うまでもなく、そんな「自己」像は虚構でしかない。その虚構性やチープさを指摘するのも、それに飛びつく彼女たちの愚かしさを笑うことも、ごく簡単なことでしかないだろう。オウムの教義なぞ漫画やアニメなどのサブカルチャーの引用でしかないし、彼女たちはそれに簡単に引っかかる「おちこぼれ」なのだ、と。だが、冷静に自分を振り返ってみるといい。彼女たちを笑う資格のある者が、一体どれだけいるだろうか? 彼女たちは少なくともカタカナ職業やカタログ雑誌の教える消費のチープさを見破ることはできたのだし、その上で「死ぬまでだまして欲しかった」からオウム真理教を選んだのだ。オウムの教義や彼女たちのチープさを嗤うことは、俺たち自身が抱えるチープな苦悩から目を背けることでしかない。 最初に述べたとおり、最近の『サイコ』ではますます過激な暴走・迷走ぶりが炸裂しており、ネット上ではその暴走に対する批判も多く見受けられるようになっている。確かにこうした迷走ぶりを嗤うことはたやすい。だが『サイコ』が抱える困難から目を反らすことは、自分自身の不毛から逃避することと同義ではないだろうか? 自己をデータベースに溶解させてしまう「宮崎的なるもの」、逆に一足飛びに虚構の「自己」像をでっちあげてしまう「オウム的なるもの」。俺たち自身の「主体」は、この両者に挟撃された、きわどい隘路の中にしかないはずだ。そして『サイコ』の登場人物たちはこの隘路を今もなお、レッドゾーンを振り切って爆走しているのである。『サイコ』の暴走を直視すること。それは、俺たち自身の抱える空虚を直視することでもあるのだ。 |
「本物だった」
宿敵・ウルフ金串を倒したジョーを、力石が目撃した瞬間。『あしたのジョー』講談社コミックス7巻より(原作/高森朝雄=ちばてつや、講談社刊)。  『あしたのジョー』より
(c)ちばてつや 規格品
『多重人格探偵サイコ』1巻より。  『多重人格探偵サイコ』より
(c)田島昭宇 大塚英志 『彼女たちの連合赤軍』
大塚英志著、角川文庫。 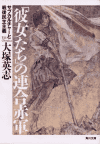 (c)大塚英志
「カタカナ職業」
ほかにプランナー、ディレクター、マーケッターなど。1980年代にはこうした職業があたかも崇高な職業であるかのように喧伝され、こうした職種に就いた人々は「ギョーカイ人」と呼ばれ、もてはやされていた。だがそのほとんどが単にホワイトカラーであるというだけの最下層労働者であり、単なる配送業を「フィールド・プランナー」と呼びかえる例すらあった。言うまでもないが、俺もまたこうした最下層労働者の一人としての出自を持ち、今もなおそうである。オウムの連中が自分と全く同種の人間だったと思うと、実に暗澹とする。 |
page 5/6
|
|
|
|
|
|
|