|
救済者としての縄文
花輪和一の描くマンガには、縄文顔の少女が虐待され、さまざまな苦難を経たのち、超自然的な力によって苦境から解放されるという筋書きのものが多い。最新作の「ニッポン昔話」などはほぼ全ての作品がこの類型に属するといってよいし、旧作の「御伽草子」にもこの種の物語が多く収められている。ここで注目しておきたいのは、こうした縄文顔の少女を救い出す超自然的存在もまた、多くの場合「縄文的」なデザインを施された宇宙人や異生物として描かれている、ということだ。

|
|
「御伽草子」(c)花輪和一
|
先に掲げたのが「龍神玉」(「御伽草子」所収)、あとに掲げたのが「かぐや姫」(同)の一コマである。いずれも逆境に苦しむ主人公に救いの手をさしのべる異生物たちだが、いずれも縄文式土器のような文様を、体に刻んだり身に纏ったりしている。こうした異類の人々は、そのグロテスクな外見とは裏腹に、決して主人公たちに危害を加えることはない。諸星大二郎の作品にもうこうした「縄文的異類」は登場するが、その多くは強大な力を持つと同時に、災いをももたらすアンビバレントな存在である。こうした「諸星的縄文」とは対照的に、花輪にとっての縄文は、「ただひたすらに弱者に対して優しい、神秘的な力を持つ人々」のしるしなのである。そしてもう一つ、花輪作品における「縄文的」な異類の人々は、奇妙な共通項を持っている。ときとして超自然的な力を発揮するこれら「縄文的異類」たちは、往々にして小さな体躯しか持たず、不器用で、弱々しい存在なのである。
縄文の「弱々しさ」
例えば「朱雀門」所収の短編、「茸の精」を見てみよう。ここに登場する茸の精もまた、縄文的な意匠を施された異類の人々だ。小人のような茸の精は、木の幹と一体化した不思議な保護者とともに、山奥でひっそり暮らしている。彼らは神秘的な力と呼べるものはほとんど持っていない。子供たちは山に出かけてはこの茸の精と遊び、そのお礼に保護者たちから金のお椀に盛られた茸を振る舞われる。茸の精は、せいぜい子供の遊び相手になるのが関の山の、イノセントな存在に過ぎないのである。
にも関わらず、大人たちは子供たちが茸の精と遊ぶのをなぜか危険視する。大人たちは村の子供を集めて目隠しし、「おまえたちは大人になったら今日一日のことはすっかり忘れてしまうんじゃ」と言い聞かせる。そして子供たちの知らないうちに茸の精の保護者をよってたかって強姦し、茸の精を皆殺しにしてしまうのである。

|
|
「朱雀門」から「茸の精」より
(c)花輪和一
青林工藝舎
|
この短編は、辛くも難を逃れた茸の精を、縄文顔の少女が背負って「山の果てまで」歩いていくところで終わる。ここには、花輪の「縄文性」が非常に高い純度で示されていると俺は思う。大人たちの忘れてしまった、自然と共感する健やかな世界。それを忘れることでしか、大人になることができない世界。それが花輪における「縄文の世界」なのだ。
花輪の作品世界における「縄文的異類」たちは、超自然的な力を持つと同時に無力な存在であるという、いっけん矛盾した性格を持っている。だが、よくよく読みこんでみるならば、これは矛盾と呼ぶにあたらない。彼らに欠けているのは、他者を抑圧してまで欲望を満たそうとする邪悪な力なのである。こうした禍々しい力を持たない替わりに、これら「縄文的異類」たちは、恩を受けたものに対して恩返しをしたり、自然と呼応したりする力はふんだんに持っているのだ。
また、花輪は別のところでこんな場面も描いている。「刑務所の中」の1シーンだ。
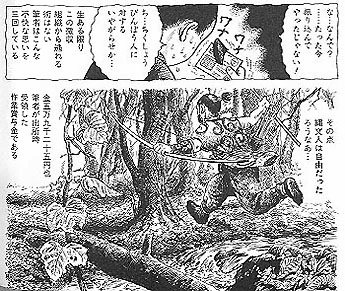
|
|
「刑務所の中」(c)花輪和一 青林工藝舎
|
花輪にとって「縄文の世界」とは、貨幣に還元されてしまうような労働とは無縁の世界だ。そこでは狩りや採集といった具体的有用労働だけがあり、健康保険の督促状や賃労働といった、抽象的な労働はいっさい存在しない。花輪における「縄文人」とは、本来あるべき人の姿、「自然人」の姿なのである。
ふたたび確認しておくが、実際に縄文人が「自然人」であったかなかったかは、あまりここでは重要ではない。花輪和一が縄文人を「自然人」として捉えていること、そしてそこに人のあるべき姿を見出していることが重要なのである。
花輪は、自らの分身である少女の顔立ちに、縄文人の特徴を帯びさせた。そして花輪和一にとって「縄文」とは、人のあるべき姿に忠実に暮らす、「自然人」の世界だった。花輪は支配者に虐待を受ける自らの分身に、「自然人」という理想の性格を付与していたのである。
以上、花輪和一作品における「丸顔・二重・どんぐり眼」の少女から出発し、花輪における「縄文」というテーマに辿り着いた。次回はこの「縄文」という花輪作品のテーマが、どのように育っていったかを追ってみたい。(後編につづく)
>>この記事に対するご意見・ご感想をお寄せ下さい。
page 5/5
|
諸星大二郎
古代の中国や日本、ニューギニアなどを舞台に、民話・伝説などを題材にした怪異譚を描くことで知られるマンガ家。諸星の「妖怪ハンター」や「暗黒神話」などの作品には、花輪同様「縄文的異類」がひんぱんに登場する。なかでも「暗黒神話」に登場する縄文的異類などは、太陽系を全滅させてしまうのだからすさまじい。花輪における弱々しい精霊のようなそれとは対照的である。

|
|
「暗黒神話」
(c)諸星大二郎
|
「朱雀門」
青林工藝舎刊、1300円。ISBN4-88379-004-5。後に述べる花輪の「屈曲するストーリー展開」がもっとも如実に現れている作品集。いくど読んでも読み手の意識を妙にすり抜けてしまう独特のストーリー展開には、汲めども尽きぬ味わい深さがある。

|
|
「朱雀門」(c)花輪和一 青林工藝舎
|
抽象的な労働
ど素人の聞きかじりを披露するようで恐縮だが、青森の三内丸山遺跡という縄文遺跡からは、「縄文尺」という長さの単位があったことが推測されるという。つまり、労働の成果についてはいざ知らず、空間については「数」に還元して抽象的に把握する能力を縄文人は備えていたのである。なんぼなんでも健康保険の督促状に苦しむ縄文人はいなかっただろうが、建屋の設計に頭を悩ました縄文人はいたことになる。誠にもってご苦労な話である。
|