|
1.
東:今回のTINAMIX インタビューでは、『アメリカの夜』(講談社)、『インディヴィジュアル・プロジェクション』(新潮社)の著者であり、現在も『アサヒグラフ』誌(朝日新聞社)で連載小説を執筆中の阿部和重さんをお招きして、本誌責任編集の砂さんと、物語構造とマンガ表現の可能性についていろいろ話していただこうと思います。とりあえず、『頭文字D』(しげの秀一作、講談社)と『湾岸ミッドナイト』(楠みちはる作、講談社)という二つのベストセラー作品を入口にしますが、話はそれから逸れて下さっても結構です。今日は僕は司会ということで、お二人の話をまとめる役目です。
そこで、この対談を前に、お二人に非常に内容の濃い基調報告を出していただきました。それを読むと、まず砂さんの方は、主にマンガ表現の視点から『D』のほうを高く評価しています。それに対して阿部さんの方は、『湾岸』の物語に注目しているということで、ここにくっきりと対照があります。
まず『湾岸』の方から話を要約すると、この作品は、深夜の高速を300Kmを超えるスピードで走る「走り屋」たちの物語であり、アキオという高校生の主人公が「悪魔のZ」と呼ばれる呪われた車を手に入れ、危険なバトルに巻き込まれるところから話が始まります。しかし実際には、アキオの登場頻度は途中から減り、むしろ、次から次へと新しい登場人物が現れては、彼らが湾岸を走ることに取り憑かれるさまが描かれることになる。そこでの「走り」とは、どこにもゴールがない、そんな人生の無意味さそのものの隠喩になっているわけですね。
それに比べると、『D』の方は典型的な対決もので、最初の敵がいる、それを倒すともっと強い敵が来た、最初ライバルだと思ってたやつが実は味方になって、さらに次のステージに話が進むという展開になっている。実際に、話の中心となるドリフトバトルの舞台は最初は群馬県の赤城山なわけですが、今の連載では県外遠征へ出かけているし、今後はプロのレーサーを目指すという話にもなっている。ここに『湾岸』との違いがあって、後者ではそういうシステムになってない。湾岸で最速になったから、次は大阪環状線を制覇して、さらには国外のフリーウェイに、みたいなことにはぜんぜんならなくて、ずっと首都高を走り続けている。しかもそのコースは、環状一号線と湾岸高速のあいだを回っているだけで、文字通りゴールがない。スピードという点も、サーキットで最速を出した登場人物があとで首都高に戻ってくるドラマが丁寧に描かれていることから分かるように、公道での走りを選んだ時点で、あきらかに諦めがある。しかも、峠でのドリフトバトルとは違って、湾岸でのバトルは誰も計測者がいないし、勝ったか負けたかもとても主観的な世界なんですね。おそらく阿部さんが評価されているのは、そういう形で、『湾岸』が対決モデルを乗り越えてるところにあるのだと思います。そうしたお互いの立場を前提に、まず砂さんから話を始めてもらえれば、と思うのですが。
砂:基調報告で、私はスポーツを主題にできるおそらく唯一のジャンルとしてのマンガ、なんてことをぶちあげているのですが、まずこれについて小説家であり、映画評論もされている阿部さんに伺いたいんです。自分が知る限りでも、明治時代の文学者たちの書簡の中に「最近スポーツとか盛り上がっていて嫌じゃないですか……」なんて書いてあるものがあった。たしか寺田寅彦が森鴎外に出した手紙だったと思うんですが。そこではスポーツは文学の題材になるどころか完全に排除されている。
そうした文学側からの言及の中で唯一毛並みが違うなと感じたものはムージルの『特性のない男』です。こうした30年代頃の東欧文学にはスポーツの痕跡がいくつかあって、『特性のない男』では、軍人、技術者、数学者と野心を抱いて職を渡り歩く主人公が、ある朝新聞で「天才」の称号がボクサーどころかとうとう競走馬についているのにショックを受けていたりする。「馬も天才になる時代か」と。そこでぐったりしつつとりあえず一年間の隠居生活をはじめて特性のない男になる、という話なんですよ。これはスポーツに対してユーモアを示してますよね。他にも、たとえばゴンブローヴィッチの『フェルディドゥルケ』では、テニスをする女学生と文学青年が対決するとかがある。
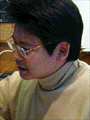 一方映画では、ひとつの成功例として『ロッキー』(ジョン・G・アビルドセン監督、1976年)があると思うんですよ。でもこれは、引退しかけたロートルボクサーの復活逆転劇というボクシングにもともと内在する決定的なロマン、黄金パターンによって可能になっているんで、ちょっと例外かなと。それで最近になると、もはや『メジャーリーグ』(デビッド・S・ワード監督、1989年)みたいにコメディの要素を入れないとできなくなっているのかな、とか考えているのですが。 一方映画では、ひとつの成功例として『ロッキー』(ジョン・G・アビルドセン監督、1976年)があると思うんですよ。でもこれは、引退しかけたロートルボクサーの復活逆転劇というボクシングにもともと内在する決定的なロマン、黄金パターンによって可能になっているんで、ちょっと例外かなと。それで最近になると、もはや『メジャーリーグ』(デビッド・S・ワード監督、1989年)みたいにコメディの要素を入れないとできなくなっているのかな、とか考えているのですが。
阿部:文学に関しては仰る通りかもしれません。マルセル・プルーストの『失われた時を求めて』について考えてみたんですが、あれだけ長い小説のなかでスポーツの場面を全然思い出せないんですよ。僕の記憶力に問題があるのかもしれないけれども。スポーツの場面を文学で読んだ記憶はないですね。ただ映画は別です。
そもそも映画は活劇が中心ですから、サイレント期からいろいろ描いていた。特に「走ること」に関しては幅広い。カーレースなんて、リュミエール兄弟の作品(『花で飾った自動車のコンクール』、1899年)ですでに撮られている。グリフィスの有名な『イントレランス』(1916年)でも、サスペンスを最大限に盛り上げるためにカーチェイスの場面が後半に設定されていますし、キートンの作品はどれもスポーツ映画みたいなものです。
車以外でスピード感を描き出すものとしては、やはり馬の走る姿があります。馬というのは、リュミエール兄弟の初作品『工場の出口』(1895年)に登場しているくらいですから、映画にとって重要な被写体で、代表的な「馬の作家」としてはジョン・フォードがいます。あるいは、これは馬の映画ではありませんが、フォードがトーキー初期に撮った『周遊する蒸気船』(1935年)という蒸気船レースの映画があります。この映画は『イントレランス』の筋立を踏襲してますが、それをトーキーの形式に再構成している。主人公と敵役が何かを賭けてレースを行い、最後に主人公が勝利するまでを90分内で描く上での説話技法を、模範的に示した映画なんです。ちなみにこうした展開のレース場面は未だに撮られていて、昨年公開された『スター・ウォーズ/エピソード1/ファントム・メナス』(ジョージ・ルーカス監督)にすらある。
カーチェイスに関しては昔からギャング映画のなかで盛んに描かれていましたが、カーレースを描く映画も、元々プロのレーサーでもあったハワード・ホークスが1932年に『群衆の喚呼』を発表している。60年代になると、ハリウッドの撮影所システムが機能不全に陥ってロケーション中心の映画制作になったことも関係していると思われますが、カーレースも多く撮られるようになる。たとえばホークスは30年ぶりのカーレース映画となる、『レッドライン7000』(1965年)を発表している。
ヨーロッパだと、1967年にポーランドのイエジー・スコリモフスキがベルギーで撮った『出発』という映画があるんです(これはあまり知られてないけれども、昨年日本で大ヒットした『バッファロー'66』(ヴィンセント・ギャロ監督、1998年)の元ネタになっている映画です)。主役がジャン・ピエール・レオで、彼は公道レースを趣味にしている美容師として登場します。店からポルシェをだまし取って乗り回し、公道レースの大会に出場するためにいろんな騒動を起こすんですが、最後はレースの出場をやめて彼女を選ぶという話なんです。映画史的にはこの映画、ヌーベルバーグの終焉を予告しているような作品なんですね。
アメリカでは、『出発』を受け継ぐかのようにモンテ・ヘルマンが『断絶』(1971年)を撮る。まさに公道レースそのものの映画で、旅の間に出会った車と賭けレースをやるんです。その旅の様子だけが、ただ淡々と描かれていく映画です。実は『断絶』のラスト・ショット(上映中のフィルムが焼き切れる)は、『出発』のラストの引用なんです。影響関係は明らかなんですが、4年後の『断絶』はより絶望が深まってる感じです。
その後は、公道レースに関しては、現実にアメリカで行われている「キャノンボール・レース」を題材にした映画がいくつか撮られていますね。カーチェイス場面は、70年代にはアクション映画に不可欠な要素になったといっていい。そんなわけで映画では、自動車の走行場面はもはや撮り尽くしたように思えるんです。70年代は、『ダーティ・ハリー』(ドン・シーゲル監督、1971年)なんかでもそうですが、高低差の激しいサンフランシスコの坂道を車がばんばん走るような場面が頻繁に撮られていた。それで単純に飽きられたのと同時に、映画で車を描くことの限界っていうのが、だいたい70年代から80年代前半までに露呈したんだなと感じる。僕がそのことを深く実感したのは、やはりマンガを読むことによってなんです。映画におけるカーレース場面を描くことの限界が見えたなと思ったんですよ。それはどの部分かというと、最も大きいのは時間処理の問題だと思うんです。
砂:映画でもたしかにカーレースものはあるんですよね。他のスポーツはどうですか、サッカーとかは?
 阿部:サッカーもあるんですよ。たとえば『ロッキー』のシルベスター・スタローンが主演している『勝利への脱出』(ジョン・ヒューストン監督、1980年)です。これはペレまでが出演しているサッカー映画で、第二次大戦中、ナチス占領下のパリでドイツ軍のサッカー・チームと捕虜チームが試合をするという映画です。当然ヒトラーなんかも観戦しているわけですが、試合に勝利しつつ、パリから脱出するという話なんです。他には、アイスホッケーを題材にした『スラップ・ショット』(ジョージ・ロイ・ヒル監督、1977年)というおもしろい映画がある。女子プロレスだって、『カリフォルニア・ドールズ』(ロバート・アルドリッチ監督、1981年)という傑作があります。ちなみに僕はこれを中学生のころに見て、大変感激しました。 阿部:サッカーもあるんですよ。たとえば『ロッキー』のシルベスター・スタローンが主演している『勝利への脱出』(ジョン・ヒューストン監督、1980年)です。これはペレまでが出演しているサッカー映画で、第二次大戦中、ナチス占領下のパリでドイツ軍のサッカー・チームと捕虜チームが試合をするという映画です。当然ヒトラーなんかも観戦しているわけですが、試合に勝利しつつ、パリから脱出するという話なんです。他には、アイスホッケーを題材にした『スラップ・ショット』(ジョージ・ロイ・ヒル監督、1977年)というおもしろい映画がある。女子プロレスだって、『カリフォルニア・ドールズ』(ロバート・アルドリッチ監督、1981年)という傑作があります。ちなみに僕はこれを中学生のころに見て、大変感激しました。
大体こんな感じで、スポーツ映画って、バスケットでもゴルフでもアメリカン・フットボールでもビリヤードでも、何でもあるんです。
砂:もちろん数えていくとスポーツを扱った映画はたくさんあると思うんですが、たとえばマンガの場合だと、マンガ名作集といった形で集めた時に、非常に多くの割合をスポーツものが占めたりするんですよ。そういうセレクションした場合には、ほとんどマンガにおけるメインジャンルに近い印象を受ける。映画はさすがにそこまでではないですよね。
阿部:スポーツがメインだってことはないですね。少なくともマンガほどではないでしょう。ではなぜそうなるかってことを考えると、さっきの時間処理の話と繋がるんですけど、映画はだいたい一時間半から二時間のあいだで終わるのが通例なんですが、そのなかに試合も収めなければならない。もちろん野球をリアルタイムでやっていけば、二時間で終わらないこともないけれど、そこでは心理描写をやる余地はまったくない。単なる試合の再現で終わる。単なる試合の再現なら、プロ野球を見に行けばいいわけですから、客は入らないから当然やらない。結局、様々なサブ・エピソードを織り交ぜながら物語りますから、描写可能な試合場面は限られてしまうわけです。これが娯楽映画の限界ですね。
とはいえ、映画で描かれたスポーツ場面からある種のカタルシスを得ることは今なお少なくありません。実際アメリカでは、相変わらずスポーツ映画は数多く撮られているし、人気も高い。でも日本人の我々からすると、映画よりもマンガの方が、スポーツの過程を詳細に描いてしまっていることを知っている。その部分はやはり見逃せない。
|