|
|
|
多重人格探偵サイコ オウム真理教的、宮崎的
■『北神伝綺』、その実存的煩悶ここまでの議論を整理すると、「大塚英志」という人格は、「内面の人」と「ゲームの人」という二つのパートに解離しており、これを「評論家」と「原作者」という二つの職業に振り分けてきた、ということになる(誤解のないよう言っておくと、こうした使い分けは大いに「あり」だし、単純に批判されるべきものでもない、と俺は思う。個人としてはエコロジストでも、環境を破壊する大企業に勤めている、そんな「生きるための解離」を抱える人間はいくらでもいるし、それを他人がとやかく言うことはできない)。ある時期までの大塚は明らかにこうした乖離を生きていたし、むしろ器用すぎるくらいに使い分けてきた、と俺は思う。だが大塚は、やがて大きな変化を見せはじめる。それまでの大塚なら純然たる「ゲームの人」として取り組んできたはずのまんがのストーリーに、突如「内面」を侵入させはじめたのである。『北神伝綺』と題された作品が、その先駆けである。 『北神伝綺』の狂言回しとなるのは、民俗学者の柳田国男である。柳田はかつて「日本には山人と呼ばれる先住民がいた」とする「山人論」を唱えた人物だが、この柳田の山人論は、当時の天皇制イデオロギーと鋭く対立するものだった。天皇制イデオロギーのキモとなるのは、「日本人は単一民族であり、天孫降臨によって地上に降り立った天皇家の人間こそ最初の日本人だ」という虚構の神話だ。そこでは「山人」などという民族の存在も、「彼らの方が天皇家より先に日本にいた」とすることも許されない。自説と天皇制との矛盾を悟った柳田は、「山人論」を棄てて転向。軍部による「山人狩り」に加担するばかりか、山人の生き残りである門弟・兵頭北神を利用し、より徹底した「山人狩り」を行おうとする。『北神伝綺』はこの兵頭北神を主人公として、陰惨極まりない山人狩りを描いていくのである。 『北神伝綺』で「ゲームの規則」に当たるのは天皇制イデオロギー、あるいは単一民族神話である。「ゲーム」の目標は山人の生き残りをひとり残らず抹殺することであり、従来のように大塚が「ゲームの人」として原作を書き綴るのであれば、ひとり残らず山人を殺戮してメデタシめでたし、となるはずであった。ところが柳田はかつて「山人論」を唱えた張本人、北神には山人の血が流れている。このためゲームの規則に忠実になればなるほど両者は自己否定を迫られるのである。ここでは「ゲーム」と「内面」とが真っ向から対立しており、主人公は実存的煩悶を味わうことになる。 この作品の終結部では、北神は「ゲーム」を続行するか「内面」を維持するかの二者択一を迫られる。結末は伏せるが、北神が下した結論はあまりにも苦く、暗い。「内面の人」と「ゲームの人」の二面を小器用に使い分けてきたはずの大塚は、ここで明らかに「壁」にぶつかっている。ただし、それは単にネタ切れとか、オチがつかないとかいったレベルの壁ではない。単なる「おはなし」が「作品」になるための臨界点に、ここでの大塚は辿り着いているのである。  【図3】 【図3】『北神伝綺』の終幕、もはや進退窮まった兵頭北神が、四方八方から問いつめられる場面。ここで問いつめられているのは大塚英志自身の態度でもあるのだが、さて、その結末やいかに。 『北神伝綺』より (c)大塚英志/森美夏 ■煩悶から叛逆へ、ゲームからその破壊へとはいえ、『北神伝綺』にはいくつか不徹底な点もある。柳田が山人論を棄てて転向するのは、急速に右傾化を強めていく時局に迎合したからだ。だが柳田に破門され、自らも山人の血を引く北神までが、なぜ柳田の意のままに山人狩りを行う必要があったのか。この最も大きな問いに、『北神伝綺』は答えていない。また『北神伝綺』の登場人物たちは、「ゲームの規則」に疑問を感じ煩悶しつつも、その規則を逸脱することがない。臨界点すれすれの地点まで達していながらも、何か振り切れていない印象がそこには残る。 だが、『多重人格探偵サイコ』の登場人物たちは、これとは明らかに違っている。彼らは「ゲームの規則」を定めた者の正体を突き止め、その規則に対して公然と叛逆しようとする。『サイコ』の登場人物たちの行動は、もはや「煩悶」などという生ぬるい領域を踏み越えている。彼らは一様にレッドゾーンを振り切っているのである。この作品をもって大塚は「作品」への臨界点を超えた、と俺は思う。『多重人格探偵サイコ』は大塚にとっての「転回」だったのである。 なぜ大塚はこうした「転回」を迎えてしまったのだろうか。もちろん、ストーリー・テラーとしての円熟もあるだろう。だが、それだけではないような気がする。大塚は「評論家としての姿勢」と「実作者としての姿勢」を、何食わぬ顔で使い分けていくことも可能だったはずだ(余計なお世話だが、ひょっとするとそちらの方がビジネスとしては上手くいったかもしれない)。だが、彼はそうしなかった。大塚の中の何かが、この解離に対して苛立ち、「ゲームの規則」を破壊させるような転回を強いたのだ。では、そのような転回を大塚に強いたものとは一体、何なのか。 ここで俺は、ある犯罪者のことをどうしても思い出してしまう。大塚英志が一貫してその公判に立ち会い続けた殺人事件の被告人。数次に渡る精神鑑定を受け、一度は「解離性同一性障害(いわゆる多重人格)」の診断を受けた男。そう、連続幼女殺人事件被告・宮崎勤である。俺は大塚の「転回」の背景には、この宮崎の存在があるような気がしてならないのだ。では、宮崎勤とは、一体どのような人間だったのだろうか。 |
『北神伝綺』
大塚英志+森美夏、角川書店刊。上、下巻(完結)。 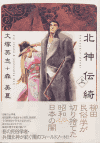 (c)大塚英志
森美夏 柳田国男
1875~1962年、民俗学者。森鴎外・田山花袋らの自然主義文学者と交流。東京帝大政治科を卒業後、農商務省に勤務。宮崎県・椎葉村、岩手県遠野への旅行をきっかけに『遠野物語』を出版、民俗学者に。「平地民とは人種の異なる『山人』が実在する」とした山人実在論を唱えるが、南方熊楠の批判にあい、自説を放棄、転向。以来、平地定住農耕民=常民を自説の中心に据え、山間部の非農耕民や、非定住民をことさらに無視した「常民研究」を行うようになった。転向以降の研究態度は多分に時局迎合的な面があったといわれ、今日では多くの研究者の批判するところとなっている。『北神伝綺』はこうした柳田の来歴を踏まえて描かれたものと思われるが、「山人狩り」はフィクションである。 兵頭北神
大塚のあとがきによれば、「同名の人物をモデルにしている」とされている。モデルとなった兵頭北神は生没年不詳。古書店店主を営むほか、私家版でオカルト関係の書物を多数翻訳。柳田の私的リサーチャーを勤めていたとされる。昭和6年頃に渡満し、終戦直前に客死。その人物像を巡ってはいくつかの著作や文書が存在しているが、ほぼ全てが偽書である。 振り切れていない
大塚のあとがきによれば、『北神伝綺』は満州を舞台にした壮大なストーリーになる予定だったが、掲載誌の休刊によって打ち切りになったのだ、とある。このあとがきを信用するなら、結末の「振り切れなさ」感は連載打ち切りによるもの、ということになる。なお本作には姉妹作として『木島日記』(大塚英志+森美夏、1、2巻既刊、角川書店刊)があり、『エースネクスト』(角川書店)誌上にて現在も連載継続中である。 宮崎勤
1962年~、連続幼女殺人事件被告。東京工芸短大映像技術科卒業後、印刷会社に就職するが退職。以降は両親の経営する印刷工場に勤務。1988年から翌年にかけて、連続して4人の幼女を誘拐して殺害。遺体をビデオ撮影した後に切断、遺骨の一部を食べたほか、被害者の両親や新聞社に宛て、「今田勇子」の名で遺骨や犯行声明文を送付した。1989年、ほかの幼女を裸にして撮影しようとしたところを幼女の両親に発見され、同日逮捕。拘留中に一連の犯行を自供し、被告となる。本人は犯行の事実関係のほぼ全てを認めているが、「今田勇子」に関わる部分についてのみ否認している。公判では簡易鑑定・一次鑑定・二次鑑定と三度に渡る精神鑑定が行われ、二次鑑定では意見が対立(「分裂病」とする鑑定と「多重人格」とする鑑定の二派)。都合四種類の鑑定が提出される異常事態となった。その後、東京地方裁判所は「責任能力あり」とする簡易鑑定と一次鑑定を採用。精神病との判定を下した二次鑑定を不採用として、検察の求刑通り死刑を宣告した。二審の東京高裁でも一審の判決を支持、死刑の判決を下したが、弁護側はこれを不服として、2001年7月10日、最高裁に上告を行った。なお宮崎には著書として、獄外との往復書簡をもとにした『夢のなか』(創出版刊)があり、大塚はこの書物に「解説」として一文を寄せている。  (c)宮崎勤
|
page 3/6
|
|
|
|
|
|
|