■ポストモダンとは何か?=「大きな物語」の崩壊
- ~1970
- 大きな物語が機能している段階(理想の時代)
=ポストモダン以前
- 1970 ~1995
- 大きな物語が虚構として代補される段階(虚構の時代)
=ポストモダン第1 期
- 1995 ~
- 大きな物語が消滅する段階(動物の時代)
=ポストモダン第2 期
- 理想の時代から虚構の時代への特異点…連合赤軍
- 虚構の時代から動物の時代への特異点…オウム真理教
■虚構の時代から動物の時代へ(fig.1 )

物語の時代からデータベースの時代へ
オタク系文化での現れ
- 物語優位からキャラクター優位へ
- 作家性の神話から萌え要素のデータベースへ
■『新世紀エヴァンゲリオン』の二重性
- 大きな物語の自己崩壊
=「虚構の時代」の終わりを告げるもの
- 二次創作の爛熟
=二次創作を模倣する原作という捻れ(TV 版最終回)
→オリジナルがシミュラークルをシミュレーションしてしまう
時代
→シミュラークルの背後にあるデータベースの台頭
→萌え要素化された綾波レイや惣流アスカ
■データベース化するキャラクター文化(fig.2 ,fig.3 )

大塚英志「個々の作品の背後には大きな物語がある」(物語消費論)
しかし1995 年以降、この図式は成立しないのではないか?
むしろ…
仮説「個々の作品の背後には設定やキャラクターのデータベース
があり、さらにその背後には「泣き」や「萌え」のデータベース
がある」(データベース消費論)
- 例:ポスト・エヴァンゲリオンの時代を象徴する
『デ・ジ・キャラット』
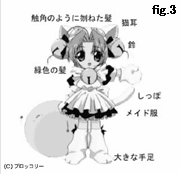
■データベース消費の一例:ノベルゲーム(fig.4)

システム(データベース)のレベルとシナリオ(シミュラークル)
のレベルで分離した消費行動